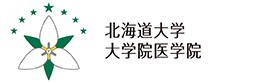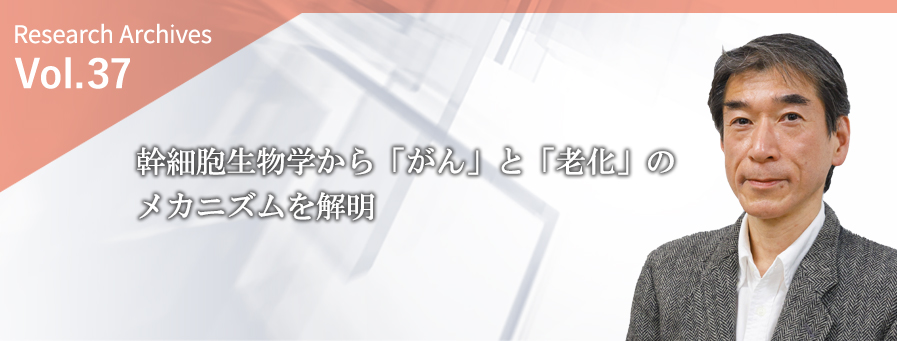
北海道大学大学院医学院 癌病態学講座 幹細胞生物学教室
教授近藤 亨癌病態学講座
- 1994年、大阪大学大学院医学研究科博士課程修了(生理系)(医学博士)(指導者:岡田善雄 教授)
- 1994~1998年、大阪バイオサイエンス研究所 第一研究部 特別研究員(指導者:長田重一 部長)
- 1998~2000年、MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, University College London(日本学術振興会海外特別研究員)(supervisor: Prof. Martin C. Raff)
- 2000~2001年、MRC Laboratory for Molecular Cell Biology, University College London, Research fellow(supervisor: Prof. Martin C. Raff)
- 2001~2002年、熊本大学 発生医学研究センター(田賀哲也 教授) 助教授
- 2002~2005年、Centre for Brain Repair, University of Cambridge, Group leader (PI)
- 2005~2010年、理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター(CDB) チームリーダー (PI)
- 2009~2012年、愛媛大学 プロテオ医学研究センター 幹細胞分化制御部門 教授
- 2012年~現在、北海道大学 遺伝子病制御研究所 幹細胞生物学分野 教授
がんや老化に関連のある膜タンパク質と液性因子の特定

2012年に本教室に就任した近藤教授は、組織幹細胞の変化の仕組みを解明し、疾病や老化との関わりを研究しています。幹細胞は、自己複製やさまざまな細胞に分化する能力を持つ細胞で、発生や組織の再生などを担っています。
「歳を取ると物覚えが悪くなったり、白髪やシワができたりしますが、これは体の機能維持に働いている組織幹細胞の機能不全や異常が原因だと考えられています。一方、がんにも幹細胞と似たような機能を持つ細胞(がん幹細胞)が存在することがわかってきました。がんや老化のメカニズムと幹細胞は関連が深いのです」と語る近藤教授。
近藤教授がこの分野に興味を持ったのは、ロンドン大学に留学中に、高等生物の中枢神経系を構成する細胞の一つであるオリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)が幹細胞化することを発見したことがきっかけでした。さらに留学先の担当教授や同僚からさまざまな示唆を得て、ケンブリッジ大学脳修復センターのグループリーダーとして独立後、がんや老化と幹細胞との関連について本格的な研究をスタート。その後、理化学研究所CDBのチームリーダーに就任し、がん幹細胞研究のモデルづくりと細胞老化研究に取り組みました。
「一般的ながん研究では、ヒトのがん細胞を免疫不全マウスに移植して疾病を再現します。しかし、そもそも正常な細胞がどのようにがんになるのか、その起源となる細胞や遺伝子変異の組み合わせについては未だ全容が明らかにされていません。私の研究では、がんの起源細胞にさまざまな遺伝子変異を加え、がんを作る細胞と作らない細胞を比較したり、マウスとヒトのがん幹細胞を比較して、がん化に関わる重要な因子の探索を進めてきました」
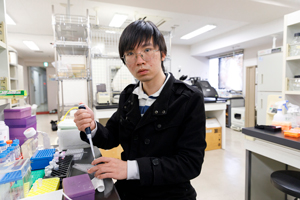
近藤教授の研究グループは、幹細胞や前駆細胞の変化がどのようにがん化・老化を決定し、疾病発症などにつながるのかを研究しています。これらの研究の中で近藤教授が注目しているのが、グリオブラストーマ(悪性度の最も高い脳腫瘍)幹細胞に特異的な遺伝子の一つである膜タンパク質と、神経系前駆細胞の老化に関わる液性因子です。
現在、幹細胞生物学教室では、次の3つのテーマを中心に研究を行っています。(1)脳腫瘍幹細胞の解析と新規治療法開発、(2)アルツハイマー病に関わる新規遺伝子の解析と治療法開発、(3)老化に関わる新規遺伝子の解析。いずれも膜タンパク質や液性因子がどのように関わっているかを解析するもので、特許取得や国内外ベンチャーとの共同研究など、さまざまな展開を見せています。
「“なぜ歳をとるのか?”のように誰もが疑問に思うことを科学的に解明することを目標として、その答えを見つけるための研究は研究者としての自己表現であり、醍醐味であると思います。その結果が未知の領域を切り開くことにつながれば更に楽しいですね」

脳腫瘍、認知症、肥満などをターゲットに最先端の研究を推進
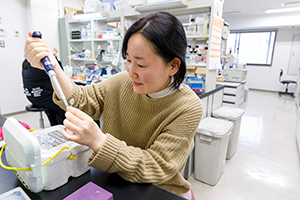
「褐色脂肪を活性化させるには、運動など体内に熱を産生する行動をとることが良いのですが、一番効果的なのは寒冷刺激と言われています。しかし、肥満の治療方法として寒冷刺激を用いることはあまり現実的ではありません。私たちの研究では、褐色脂肪だけに発現する遺伝子を見つけ出し、その機能をダウンまたはアップさせる方法を探しています」(孫講師)
孫講師らの実験では、褐色脂肪に特異的に発現する遺伝子を候補として、その遺伝子を完全にノックアウトしたマウスと通常のマウスに高脂肪食を与えたところ、遺伝子がノックアウトされたマウスは太らなかったという結果を得ました。現在は、遺伝子の分子メカニズムの解明に取り組んでいるところです。
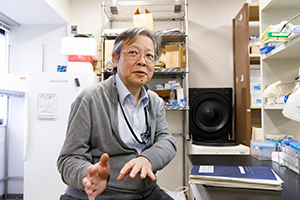
がん幹細胞は、それ自体が自己複製するとともに、さまざまながん細胞へ分化する性質を持っています。橋本助教の研究グループでは、マウスなどの脳にある悪性腫瘍の細胞を採取し、がん幹細胞性を持つものと持たないものとではどのような遺伝子の発現の違いがあるかを比較。がん幹細胞特有の遺伝子発現を特定し、それを引き起こすタンパク質や代謝産物を標的とした診断・治療手法の開発につなげる研究を行っています。
「この研究室は、近藤教授の実績をベースにした幹細胞のキャラクタリゼーションに関する高度なノウハウを有するというアドバンテージがあり、創薬や治療法の開発につながる可能性が高いと思います」(橋本助教)
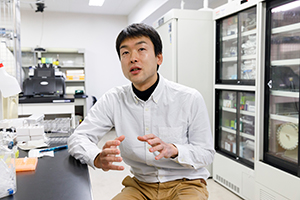
(取材:2021年11月)
活発なコミュニケーションで研究活動をサポート

新型コロナウイルスの影響でイベント等の自粛が続いていますが、以前はバーベキュー大会を開催したり、外部スピーカーを交えての食事会、大学院生が手作りしたケーキを一緒に食べたりするなど、さまざまなイベントがありました。また、研究を効率よく進めるためにラボミーティングとは別にグループミーティングを行い、メンバー同士が活発にコミュニケーションしながら研究指導や実験技術の向上を図っています。