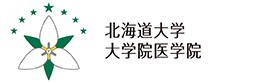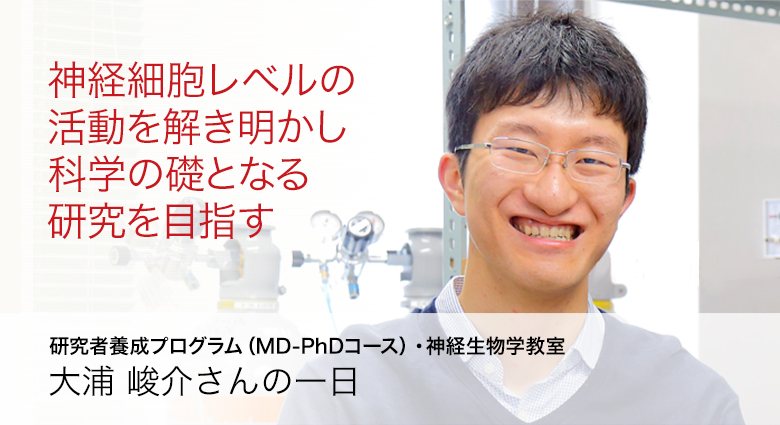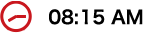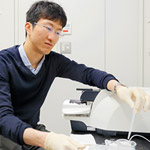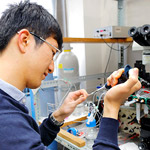-
医学科について
-
教育内容
-
入学希望の方へ
-
在学生・卒業生の方へ
-
国際交流
その他

-
医学院について
-
教育内容
-
入学希望の方へ
-
在学生・修了生の方へ
-
国際交流
その他

-
医理工学院について
-
教育内容
-
入学希望の方へ
-
在学生の方へ
-
その他

-
医学研究院について
-
組織
-
産学連携研究

大浦 峻介さんの一日(博士課程)
- HOME
- 医学院
- 写真で見る大学院生の一日
- 大浦 峻介さんの一日(博士課程)